バリエーション豊富なお祝い膳.comの食器
伝統的な漆器はもちろん、竹製、陶磁器などバリエーション多く取り揃えており、生活スタイルに合った食器を選ぶことができます。



伝統的な漆器はもちろん、竹製、陶磁器などバリエーション多く取り揃えており、生活スタイルに合った食器を選ぶことができます。
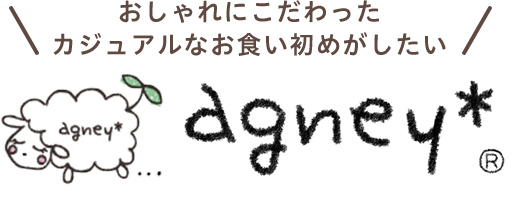
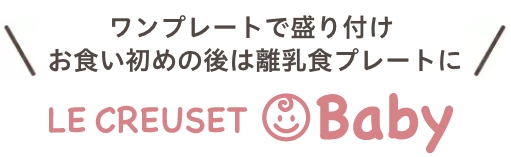


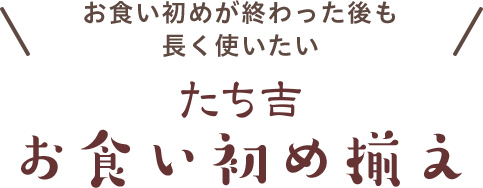
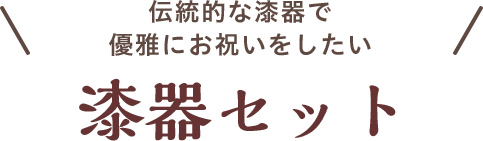
お食い初めの食器は漆器が用いられます。
お椀は漆器や素焼きで作られたものを使い、高脚の御前に割れにくく丈夫な柳の祝い箸を使います。また、祝い膳を盛り付ける食器は母方の実家が贈るのが昔ながらの習わしとしてあります。
しかし、最近では必ずしも正式なものを使わなければならないという決まりはなく、それぞれの家庭や生活スタイルに合ったお祝いをする家庭が増えてきています。
大切なのは、赤ちゃんの健康や幸せを願ってお祝いすることです。
この食器じゃなければダメということはありません。
お食い初めの儀式用に伝統的な漆器を購入する方もたくさんいますが、漆器は日常的に扱いにくい面もあり、お食い初めだけの為に正式な食器を購入することを迷われるのも無理はありません。
最近では日常使いできる食器を買ってお祝いするケースも増えています。また、お食い初めのタイミングで今後も使える実用性の高いベビー食器セットを一式そろえる家庭もあります。
伝統や形式にとらわれる必要はないので、状況や好みに合わせて準備しましょう。

お食い初めの正式な食器を購入したい方、1回だけのために購入するのを迷っている方、
当店ではお食い初め食器の販売とレンタルを行っております。


ディズニー柄もあります!


日本古来の儀式、お食い初め。しきたりに習って本格的に行いたい方におすすめのお食い初め漆器セットです。節句やお誕生日などお子様の様々な儀式に使用できます。男女で色が異なり、男の子は内外ともに朱色の漆器、女の子は外側が黒色、内側が朱色の漆器です。プレゼントとしても喜ばれます。
漆器は日常的に扱いにくい面もあり、お食い初めだけの為に正式な食器を購入することを迷われるのも無理はありません。お祝い膳.comでは、リーズナブルなレンタルのご提供も行っております。
※ご使用後は必ず洗浄してからご返送願います。
※運送会社の着払伝票を同梱しておりますので、伝票記載の集荷方法にて運送会社にお渡し下さい。
※電話申込・インターネット申込、お近くの取り扱い店(コンビニ等)にお持ち込みいただくこともできます。
詳しくは利用規約をご確認願います。
伝統的な漆器の場合は、男の子と女の子で色が異なります。
男の子は内外ともに朱色の漆器、女の子は外側が黒色、内側が朱色の漆器です。
朱色は、古来中国では高貴さの象徴であり、歳月によって変色や消滅しないなど、不老不死を希求する人たちに愛用されてきました。日本でも朱は神社・仏閣、高貴な物やおめでたいものに朱色を使ったようです。古来日本では男子の誕生は尊いものであったことから、男子用の器には全面朱色の器が使われ、女子の器は内側だけ朱色の器を使ったようです。
男女の違いは、地域によっては逆転するケースもあり、最近では男女を問わず、「祝い」の意味を持つ赤の漆器を使うことが一般的になっています。
男の子

女の子

和食作法 の 「本膳料理」 と同じ器の組み合わせになっています。
上記は代表的な一例であり、平椀・つぼ椀・高杯は、仏教の宗派によって配置が異なります。
臨済宗・曹同宗

浄土宗

真言宗・日蓮宗・天台宗

男女の違いは、地域によっては逆転するケースもあり、最近では男女を問わず、「祝い」の意味を持つ赤の漆器を使うことが一般的になっています。漆器は日常的に扱いにくい面もあり、お食い初めだけの為に正式な食器を購入することを迷われるのも無理はありません。現在では習わしにこだわらず、儀式のあとも使用できるベビー食器など、家庭で簡単に用意できる食器で儀式を行うことが多いです。